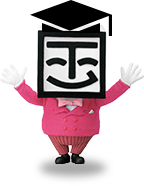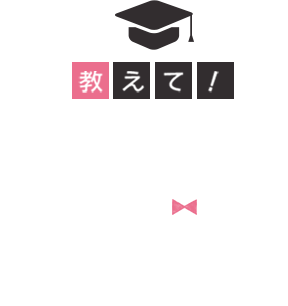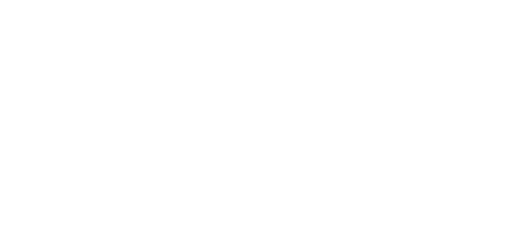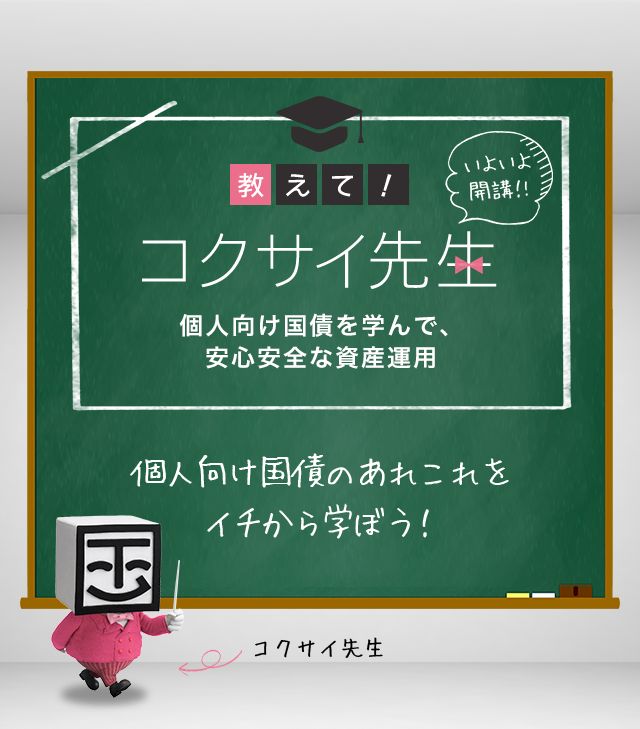

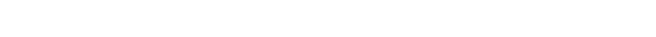
よくある質問
-

個人向け国債は、どのような商品ですか。また、どのような種類がありますか。

-

個人向け国債は、個人の国債保有を促進するために導入された商品であり、1万円単位で始められ、中途換金もできるなど、個人の方が購入しやすいようさまざまな工夫が盛り込まれています。原則として個人の方だけが保有できます。
(注)平成19年7月から特定贈与信託の受託者である信託銀行及び信託業務を営む金融機関も保有できるようになりました。
個人向け国債には、「個人向け利付国庫債券(変動・10年)」(以下、「変動10年」)と、「個人向け利付国庫債券(固定・5年)」(以下、「固定5年」)、「個人向け利付国庫債券(固定・3年)」(以下、「固定3年」)の3種類があります。 「変動10年」の商品性についてはこちらを、 「固定5年」の商品性についてはこちらを、 「固定3年」の商品性についてはこちらをご覧ください。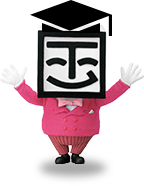
-

それぞれの商品性には、どのような違いがあるのですか。

-

それぞれの商品性の違いについては、「個人向け国債の商品性の比較」を参照してください。
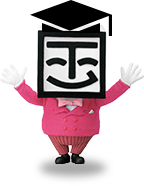
-

個人向け国債を保有することができる『個人』とは、どのようなものですか。
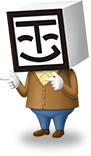
-

個人向け国債を保有することができる『個人』とは、自然人を指します。マンションの管理組合などの人格なき社団等は個人に含まれないため、保有することができません。
ただし、特定贈与信託の受託者である信託銀行及び信託業務を営む金融機関は、例外として保有することができます。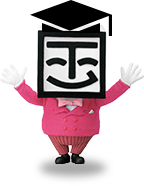
-

個人向け国債は、国債証券(券面)が発行されないとのことですが、どのように管理されますか。また、保有していることをどのように確認できますか。
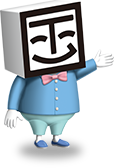
-

個人向け国債を含め、平成15年1月27日以降に発行される国債は、平成15年1月から施行された「社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)」に基づき発行されます。(同法に基づき発行される国債を「振替国債」といいます。)
振替国債は、券面が発行されないペーパーレスの国債ですので、金融機関に開設していただく国債の振替口座に記載または記録することによって管理されることになります。
個人向け国債を含め、国債の売買取引をされた場合には、金融機関が発行する取引残高報告書や通帳等で保有額を確認することができます。金融機関によって取り扱いが異なりますので、詳しくは金融機関にお尋ねください。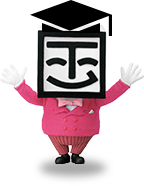
-

中途換金時に差し引かれる金額を算定する際、直前2回分の各利子(税引前)相当額に0.79685を乗じているのはなぜですか。

-

直前2回分の各利子(税引前)相当額に0.79685を乗じているのは、国債の利子の受取時に20.315%分の税金が差し引かれているためです。