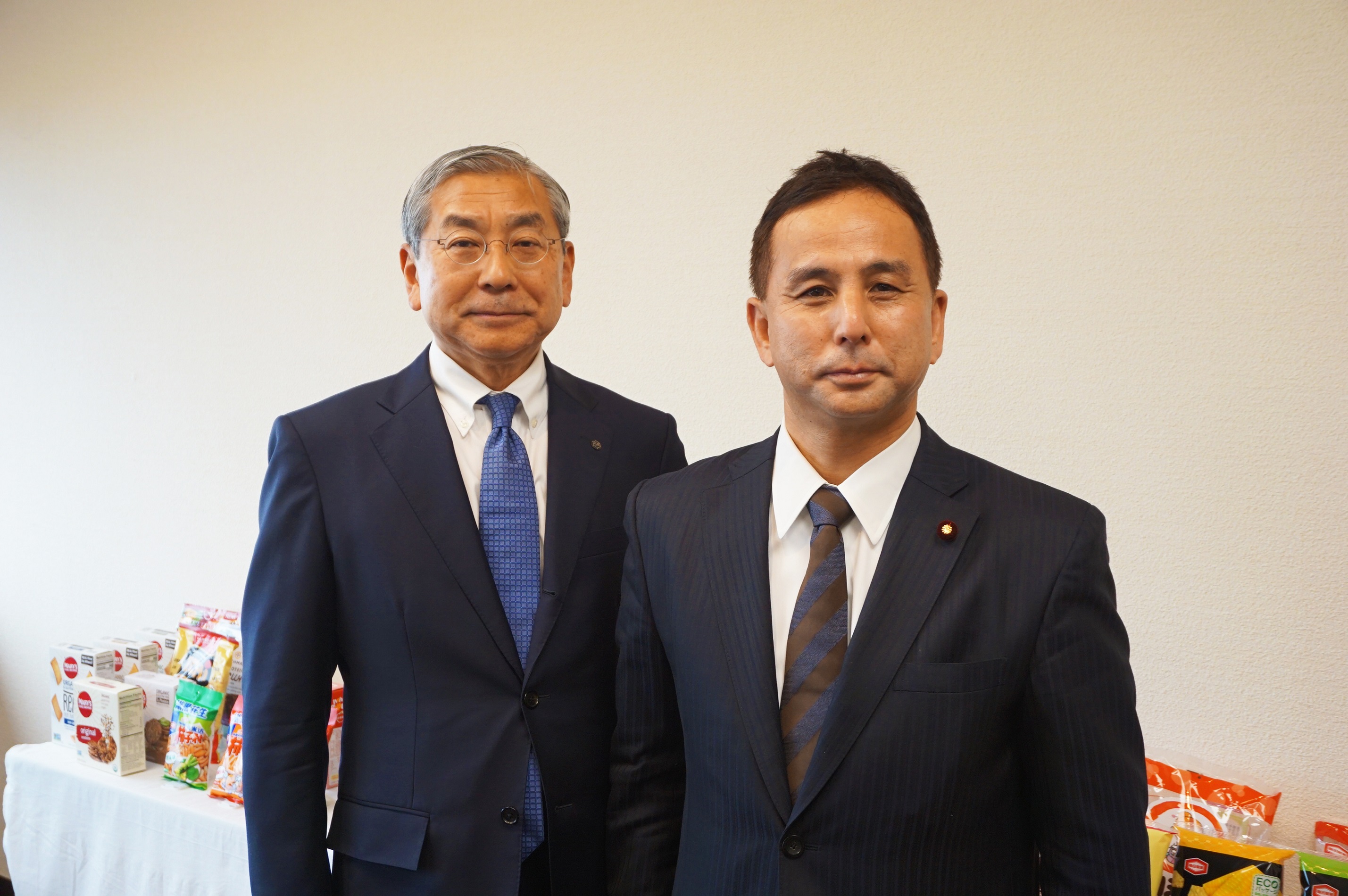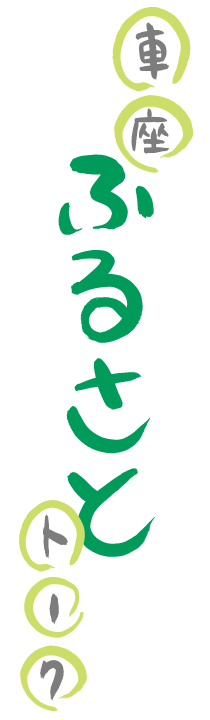
令和元年11月18日(月曜)遠山財務副大臣は、新潟県新潟市にある新潟大学において、「日本の財政の現状について」をテーマに、同大学の学生10名と「車座ふるさとトーク」を行いました。新潟県での開催は財務省として初めてです。
(注)「 車座ふるさとトーク」は、安倍内閣として、大臣、副大臣、政務官が地域に赴き、国民の皆様と少人数での車座の対話を行い、生の声をつぶさに聴いて、政策にいかすとともに、政府が取り組んでいる重要政策について説明する取組です。
参加者からは以下のような発言がありました。
軽減税率は、対象範囲などの基準が分かりにくく、私たち消費者もよく理解できていないように思う。租税3原則は、「公平・中立・簡素」とされている中、今回の軽減税率は、簡素ではないと感じる。
日本の軽減税率は外国に比べるとわかりやすいとのことだが、実際にアルバイトなど業務を行っていると、テイクアウトや外食の取り扱いに少なからず負担を感じる場面があった。
今回の消費税率引上げに関連して行われている、キャッシュレス割引、ポイント還元制度について、財務省がどのように評価しているのか知りたい。
消費税率を5%から8%に上げた際には、消費の冷え込みが大きかったと言われており、今回の消費税率引上げにおいて、1%ずつ段階的に引き上げる手法も考えられたのではないか。
低所得者保護を目的とするのであれば、給付付き税額控除などの手段も考えられるのではないか。また、財政健全化のためには、歳出面で社会保障費を削減する方法もあるのではないか。
日本の現状は、低負担中福祉となっているが、今後、少子高齢化により社会保障費が増えていくと予想されている中、社会保障制度を維持するために、主要な税のうち消費税率を引き上げることが最適なのか。
国民が将来に対して不安を覚えるのは、年金や税金について正しく理解していない面もあるのではないか。将来について特にリアリティーが増す、大学生や高校生に対する教育を充実させることが必要ではないか。
「国債をいくら発行しても、国の財政が破綻することはない。」とする、現代貨幣理論(MMT)をよく耳にする。なかなか信じがたい理論であるが、このような議論が起こる背景について知りたい。
デジタル課税について、経済のデジタル化が進む中、国際課税のあり方が議論されているが、今後どのような国際ルールや課税基準が作られていくのかを知りたい。
大規模自然災害が発生した場合には、大きな経済被害が出ると試算されている。ある程度大規模な防災対策を事前に行うことで、国民の命を守るだけでなく、財政負担を将来的に小さくすることができるのではないか。
また、車座ふるさとトーク開催にあわせて、遠山財務副大臣が亀田製菓株式会社を視察しました。