|
新聞発表 |
|
平成11年10月29日
|
|
|
|
平成12年(2000年)から発行を開始する二千円日本銀行券の主な様式等について、下記の通り決定した。 記 |
| 1. | 図柄等 | |
(1) |
表の図柄 左側に「弐千円」の文字等を配し、右側に沖縄の守礼門を配したものとする。 |
|
(2) |
すかし 沖縄の守礼門を表のものとは違った角度から見たものとする。 |
|
(3) |
裏の図柄 左側に、「源氏物語絵巻」第三十八帖(じょう)「鈴虫」その二の絵の一部分に、同帖の詞書(ことばがき)の冒頭部分を重ね合わせたもの(注1)を配し、右側に、源氏物語の作者である紫式部の絵(注2)を配したものとする。 |
|
(注1) |
「源氏物語絵巻」の「鈴虫」の絵及び詞書は、国宝で五島美術館所蔵。 |
||
| (注2) | 「紫式部日記絵巻」の一場面(「紫式部の局(つぼね)を訪(と)う斉信(なりのぶ)と実成(さねしげ)」)の絵(国宝、五島美術館所蔵)に描かれている紫式部。 |
|
2. |
その他の主な様式等 |
|
(1) |
寸法 縦76ミリメートル、横154ミリメートルとする。 (参考)現行日本銀行券の寸法 一万円券 : 縦76ミリメートル 横160ミリメートル 五千円券 : 縦76ミリメートル 横155ミリメートル 千円券 : 縦76ミリメートル 横150ミリメートル |
|
(2) |
色調 緑色を基調としたものとする。 |
|
(3) |
識別マーク 目の不自由な方にとっても他の券種との識別が容易になるよう、識別マークを現行のものよりはっきりとしたものとするとともに、左下及び右下の二箇所に、印を3つ縦に並べたもの(点字の「に」を図案化したもの)を入れることとする。なお、印の形状については、今後検討の上決定する。 (参考)現行の識別マーク 一万円券 : 左下一箇所、点字の「う」を図案化したもの 五千円券 : 左下一箇所、点字の「い」を図案化したもの 千円券 : 左下一箇所、点字の「あ」を図案化したもの |
|
(4) |
偽造防止 「すき入れ」、「凹版」、「微小文字」、「識別マーク」等の偽造防止技術を引き続き用いるほか、最新の偽造防止技術を可能な限り用いることとする。 |
|
(5) |
民間のATM・自動販売機等への対応 できる限り早期に機械による対応が可能となるよう、見本券の印刷が終了し次第業界に機器の開発のため提供するほか、見本券の印刷前においても、 日本銀行及び印刷局より適宜説明会を行う等の措置を講じていくこととする。 |
|
| |
|||||||||||||||||||||||
| ○ | 守礼門 | ・ | 首里城第二の坊門(ぼうもん)。創建は、琉球国尚清(しょうせい)王(在位1527~55年)の時代。 | ・ | 昭和8年に国宝に指定されたが、昭和20年の沖縄戦で焼失(四度目の焼失)。 | ・ | 昭和33年に復元。 | ○ |
源氏物語 |
・ | 平安時代中期(11世紀初め頃)、紫式部の作。全54帖(じょう)。 | ○ |
源氏物語絵巻 |
・ |
源氏物語の各帖から一部を選び、物語本文をもとに作成した「詞(ことば)」と「絵」を交互に繰り返す形式の絵巻。 |
||||||||
| ・ | 現存の作例として最も古く芸術的に重要なものは、平安時代後期(12世紀)のものであり、現存の絵19面及び詞37面が国宝に指定されている。 | ||||||||||||||||||||||
○ |
源氏物語絵巻第三十八帖「鈴虫」その二の絵 (国宝、五島美術館所蔵、作者不詳) |
||||||||||||||||||||||
| ・ |
左側 冷泉院( |
||||||||||||||||||||||
○ |
紫式部 |
||||||||||||||||||||||
| ・ | 平安時代中期の物語作家、歌人。 | ||||||||||||||||||||||
| ・ | 出生は、970~973年あたりと推定される。没年は不詳。 | ||||||||||||||||||||||
| ・ | 父は、藤原為時(ためとき)、母は、藤原為信(ためのぶ)の娘。 | ||||||||||||||||||||||
○ |
紫式部日記 |
||||||||||||||||||||||
| ・ | 平安時代中期(11世紀初め頃)、紫式部の作。 | ||||||||||||||||||||||
○ |
紫式部日記絵巻 |
||||||||||||||||||||||
| ・ | 鎌倉時代前期(13世紀の作)、作者不詳。 | ||||||||||||||||||||||
| ・ | 「紫式部日記」を絵巻にしたものであり、もとは全10巻程度の巻物。現在、25場面(詞書23段、絵24段)が現存する。 | ||||||||||||||||||||||
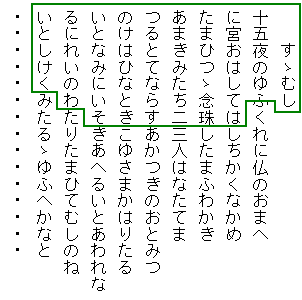
| ○ | 現代語訳 (谷崎潤一郎「新々訳 源氏物語」巻七(中央公論社)より) |
|
|
|



